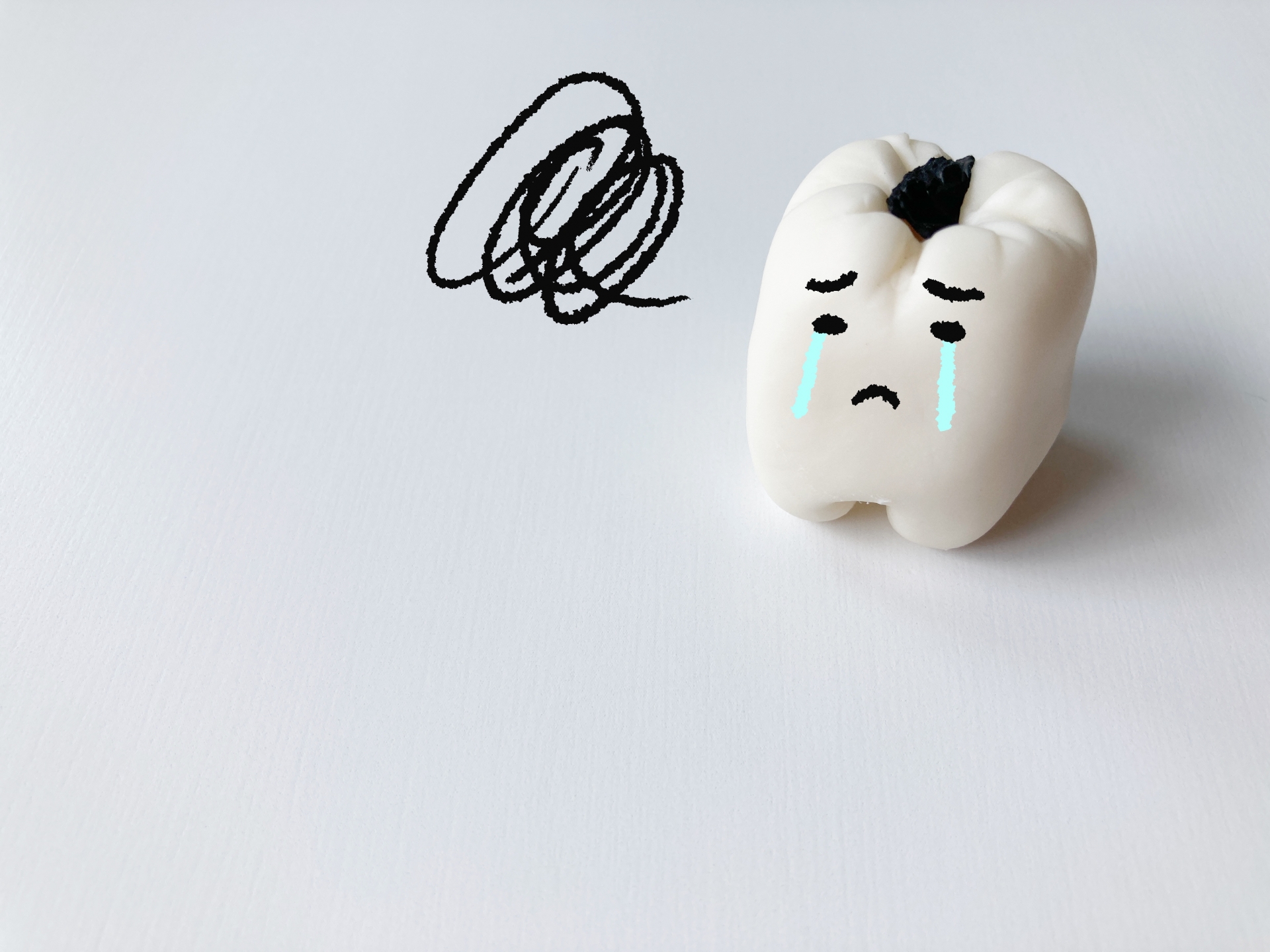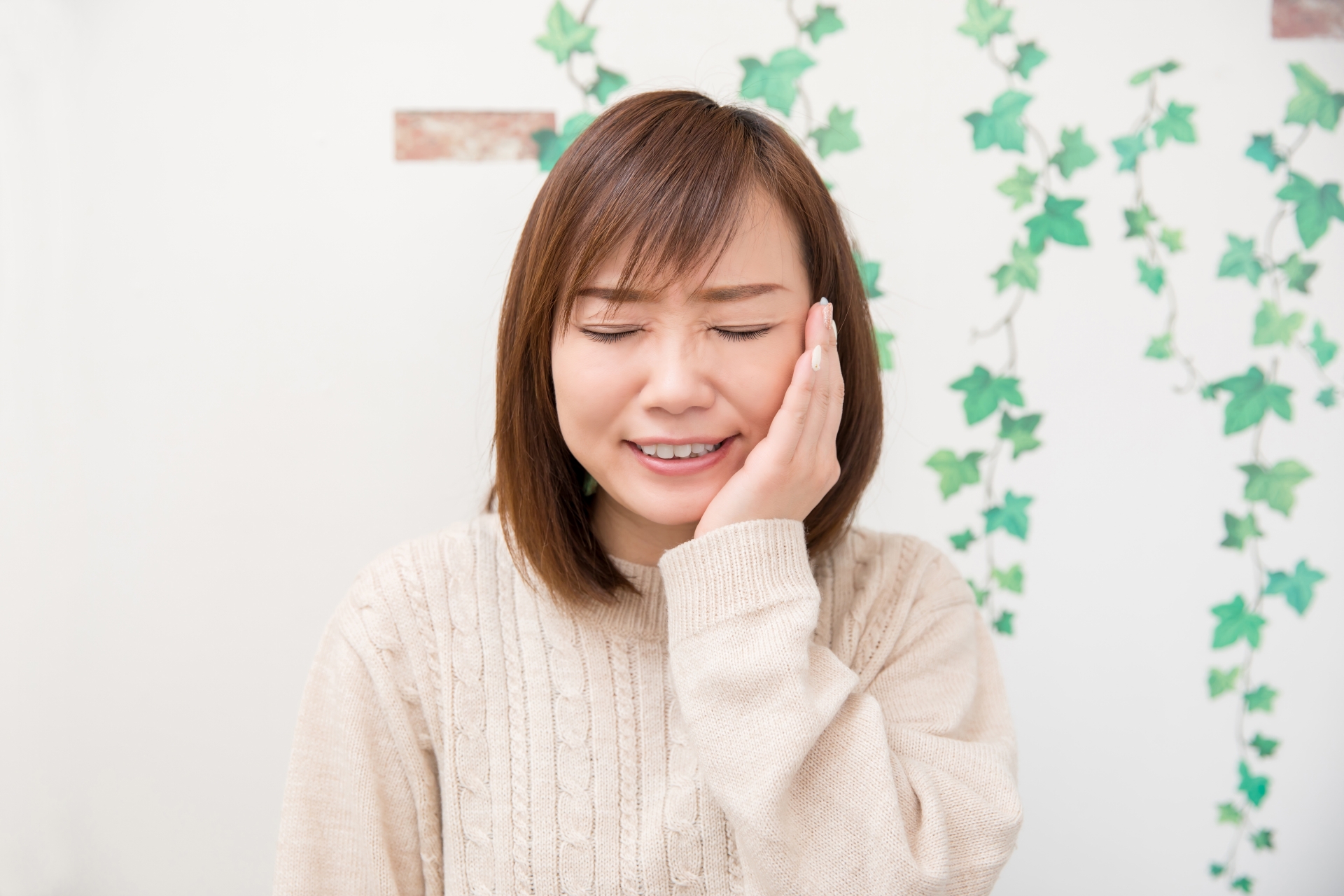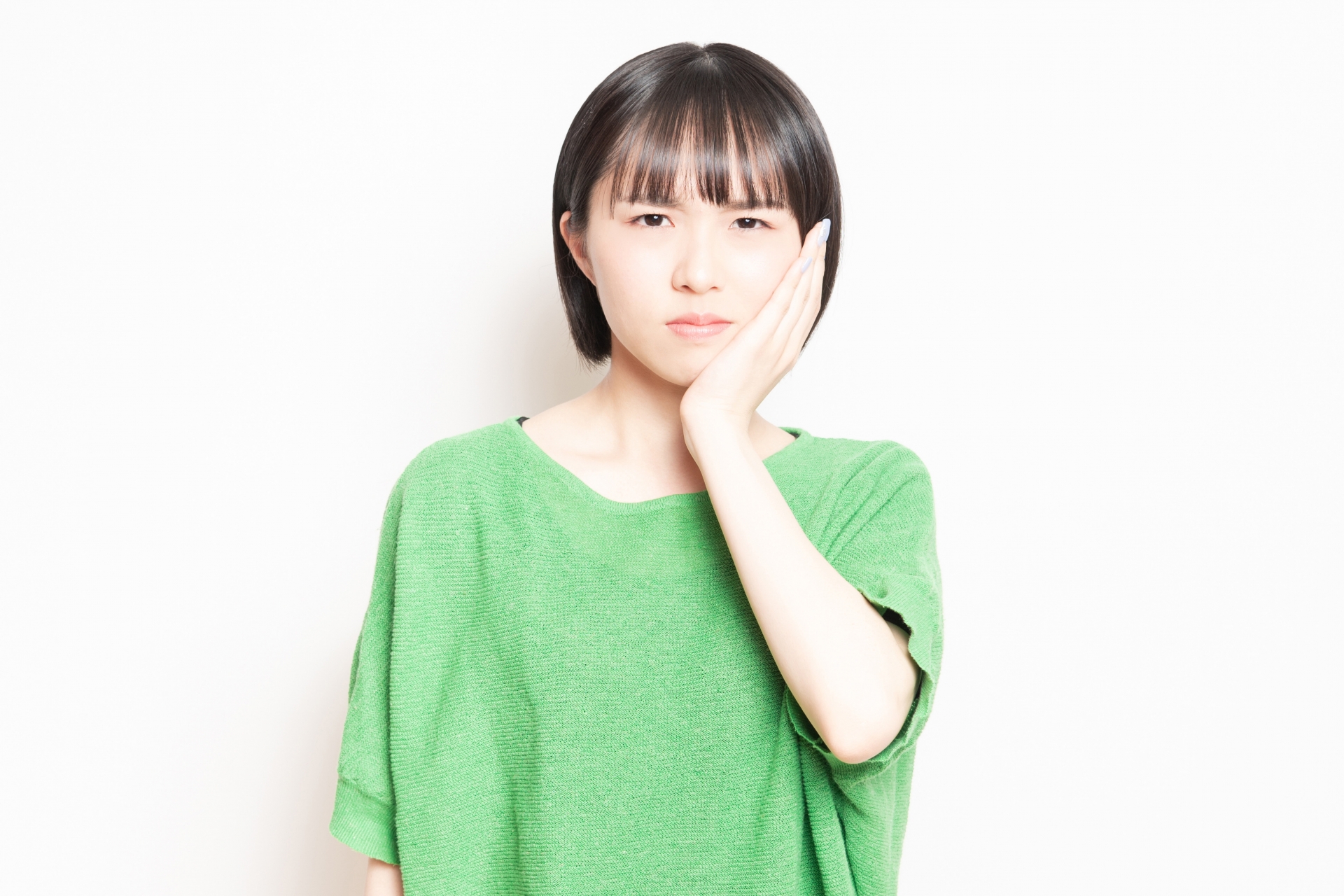
親知らずは放置すると危険?
親知らずは、多くの人にとって「抜くべきか、それとも放置するべきか」と悩ましい歯です。しかし、親知らずは虫歯や歯茎の炎症、歯並びの悪化など、さまざまなトラブルを引き起こす原因 になることがあります。特に、横向きや斜めに生えている場合、歯磨きがしにくくなり、口腔内の健康を大きく脅かす可能性 があります。
この記事では、親知らずが原因で発生する可能性のあるトラブルを詳しく解説 し、どのような対策が必要なのかを紹介します。親知らずによるリスクを減らし、口腔環境を健康に保つための知識を身につけましょう。
【目次】
- 虫歯のリスクが高まる親知らず
2. 親知らずが引き起こす歯茎の腫れ
3. 親知らずと歯並びの悪化の関係
4. 炎症が広がると起こるリスクとは
5. 親知らずが引き起こす顎の痛み
6. 口臭と親知らずの意外な関係
7. 親知らず周辺の歯周病リスク
8. 親知らずが原因で発生する嚥下障害
9. 未処置の親知らずが全身に与える影響
10. トラブルを防ぐためにできること
1. 虫歯のリスクが高まる親知らず
親知らずは口の一番奥に生えてくるため、虫歯のリスクが非常に高い歯 です。特に、斜めに生えたり、部分的に埋まった状態だったりすると、汚れが溜まりやすく、虫歯や炎症を引き起こす可能性 があります。
ここでは、親知らずが虫歯になりやすい理由と、そのリスクを減らす方法について詳しく解説 します
1-1 親知らずが虫歯になりやすい理由
親知らずは他の歯に比べて、虫歯になりやすい特徴を持つ ため、特に注意が必要です。
磨き残しが発生しやすい
親知らずは口の奥に位置しているため、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが多くなりやすい です。特に、斜めに生えていたり、一部が歯茎に埋まっていたりすると、歯垢や食べカスが溜まりやすく なります。
こうした汚れは虫歯菌の温床となり、親知らずだけでなく、隣の歯まで虫歯になるリスク を高めてしまいます。
親知らずの形状が複雑
親知らずは形が複雑で、溝が深い のが特徴です。そのため、汚れが溜まりやすく、通常の歯ブラシでは除去しきれない場合が多い です。
また、親知らずが半分しか生えていない状態 では、歯と歯茎の間に隙間ができ、そこに細菌が繁殖しやすくなります。この状態が続くと、親知らずの根元部分から虫歯が進行し、気づいた時には神経まで達している こともあります。
1-2 親知らずの虫歯がもたらすリスク
親知らずが虫歯になることで、口腔内にさまざまな影響を及ぼします。
隣の歯も虫歯になる可能性
親知らずが虫歯になると、その影響は隣の第二大臼歯(奥歯)にも及びやすい です。
親知らずと奥歯の間に隙間ができると、そこに食べカスや歯垢が溜まりやすくなり、結果として奥歯も虫歯に なるリスクが高まります。さらに、虫歯の進行が早いため、気づいた時には奥歯の神経まで到達してしまうケースも少なくありません。
歯周病のリスクが高まる
親知らずが適切に生えていないと、周囲の歯茎が炎症を起こし、歯周病のリスクが高まる 可能性があります。
特に、親知らずが半分埋まっている状態では、歯と歯茎の間に細菌が入り込みやすく、炎症を繰り返す ことがあります。これが慢性化すると、歯茎が腫れたり、出血しやすくなったりするだけでなく、最終的には歯を支える骨が溶けてしまうことも あります。
1-3 親知らずの虫歯リスクを減らす方法
親知らずの虫歯リスクを抑えるためには、日常のケアが非常に重要です。
歯磨きの工夫をする
親知らずの周辺は通常の歯ブラシだけでは磨きにくいため、デンタルフロスや歯間ブラシを併用 すると効果的です。特に、親知らずが生えかけの場合や、部分的に埋まっている場合は、ワンタフトブラシ(先の細いブラシ)を使うことで、汚れをしっかり取り除く ことができます。
また、フッ素入りの歯磨き粉を使用すると、エナメル質を強化し、虫歯の進行を防ぐ効果 があります。
定期的な歯科検診を受ける
親知らずの虫歯は自分では気づきにくい ことが多いため、定期的に歯科検診を受けることが大切 です。
特に、痛みがなくてもレントゲンで親知らずの状態を確認することで、虫歯や炎症のリスクを事前に把握 できます。
1-4 抜歯すべきかの判断基準
親知らずの状態によっては、抜歯を検討する必要があります。
親知らずが完全に生えている場合
親知らずがまっすぐ生えており、周囲の歯や歯茎に影響を与えていない場合 は、特に抜歯の必要はありません。ただし、定期的な歯科検診で虫歯や歯周病のリスクをチェックすることが重要 です。
親知らずが斜め・横向きに生えている場合
親知らずが斜めや横向きに生えている場合、歯磨きが難しく、虫歯や炎症を起こしやすいため、抜歯が推奨されることが多い です。
また、親知らずのせいで奥歯に圧力がかかり、歯並びが悪化する可能性がある場合も、早めに抜歯を検討 したほうがよいでしょう。
2. 親知らずが引き起こす歯茎の腫れ
親知らずは口の一番奥に生えてくるため、正常に生えてこないケースが多く、歯茎の腫れや炎症を引き起こすことがよくあります。特に、親知らずが半分だけ生えていたり、横向きに埋まっていたりすると、歯茎の隙間に細菌が繁殖しやすくなり、痛みや腫れを引き起こすリスクが高まります。
ここでは、親知らずが原因で歯茎が腫れる理由と、その対処法について詳しく解説 します。
2-1 親知らずが歯茎を腫れさせる主な原因
親知らずによる歯茎の腫れは、細菌の繁殖や炎症が主な原因 です。以下のような要因が、歯茎の腫れを引き起こします。
磨き残しによる細菌の繁殖
親知らずは口の奥に位置しているため、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが発生しやすい です。食べカスや歯垢が溜まると、それが細菌の温床となり、歯茎の炎症を引き起こします。
特に、親知らずが一部しか生えていない場合、歯と歯茎の間に隙間ができ、そこに細菌が溜まりやすくなる ため、炎症が慢性化しやすくなります。
親知らずが横向きに埋まっている
横向きに生えている親知らずは、隣の歯や歯茎に圧力をかけるため、慢性的な腫れや痛みを引き起こす ことがあります。
また、埋まったままの親知らずは、歯茎の下で膿がたまりやすく、炎症が悪化すると腫れだけでなく激しい痛みを伴うことも あります。
2-2 歯茎が腫れると起こるリスク
親知らずによる歯茎の腫れを放置すると、さまざまなリスクが発生します。
炎症が広がることで強い痛みが発生する
親知らずの周囲で炎症が広がると、痛みが強くなり、口を開けるのも困難になることがあります。特に、膿が溜まってしまうと、顔全体が腫れるケースもあるため、早急な対処が必要 です。
全身に悪影響を及ぼす可能性
炎症がひどくなると、細菌が血液を通じて全身に広がる可能性があります。これにより、発熱や倦怠感を引き起こすことも あります。さらに、免疫力が低下していると、細菌が心臓や脳に悪影響を与えるリスクもあるため、決して軽視してはいけません。
2-3 親知らずによる歯茎の腫れを抑える対策
親知らずが原因で歯茎が腫れるのを防ぐには、日常的なケアと早めの対応が重要 です。
歯磨きの工夫をする
親知らずの周囲は磨きにくいため、通常の歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用する ことが推奨されます。特に、ワンタフトブラシ(先端が細いブラシ)を使うと、親知らずの周りの細かい部分までしっかり清掃 できます。
また、抗菌作用のあるマウスウォッシュを使用することで、口内の細菌を減らし、炎症のリスクを軽減 できます。
冷やして炎症を抑える
歯茎が腫れたときは、冷たいタオルや氷を頬に当てて炎症を抑える と、痛みが和らぎます。ただし、冷やしすぎると血流が悪くなり、逆効果になる場合があるため、10分程度冷やして様子をみる のが適切です。
2-4 親知らずの抜歯を検討するべきケース
親知らずが歯茎の腫れを繰り返す場合、抜歯を検討することも重要です。
炎症が何度も再発する場合
親知らずが原因で歯茎の腫れを何度も繰り返す場合、抜歯をすることでトラブルを未然に防ぐことができます。特に、親知らずが半分埋まっている場合は、抜歯しないと根本的な解決にならない ことが多いです。
歯並びに影響を与えている場合
親知らずが隣の歯を押して歯並びを悪化させている場合も、抜歯を検討するべき です。歯並びが乱れると、噛み合わせが悪くなったり、他の歯が虫歯になりやすくなったりするため、早めの対策が必要 です。
3. 親 知らずと歯並びの悪化の関係
知らずと歯並びの悪化の関係
親知らずが生えてくると、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。特に、横向きや斜めに生えてくる場合、隣の歯を押し出してしまい、前歯が重なったり、噛み合わせが悪くなるリスクが高まります。
この記事では、親知らずが歯並びに与える影響と、その対策について詳しく解説 します。
3-1 親知らずが歯並びを悪化させる原因
親知らずによる歯並びの悪化は、主にスペース不足や生え方の異常が原因 です。
顎のスペース不足
多くの人は、親知らずが生えてくるための十分なスペースを持っていません。顎が小さい場合、親知らずが無理に生えてくることで、隣の歯を押し出し、歯並びが乱れる ことがあります。
横向きや斜めに生えてくる
親知らずがまっすぐ生えず、斜めや横向きになっていると、前方の歯に強い圧力がかかり、徐々に歯並びが崩れる ことがあります。特に、前歯が重なってしまうと、見た目の問題だけでなく、噛み合わせの悪化や虫歯・歯周病のリスクも高まります。
3-2 親知らずによる歯並びの悪化が引き起こす問題
歯並びが崩れることで、見た目だけでなく、さまざまな健康リスクが生じます。
噛み合わせのズレ
親知らずが歯を押すことで、上下の歯の噛み合わせがズレてしまうことがあります。これにより、食事の際にしっかり噛めなくなったり、顎に負担がかかることで顎関節症のリスクが高まる 可能性があります。
歯の重なりによる虫歯・歯周病のリスク
親知らずが原因で歯並びが崩れると、歯が重なり合い、ブラッシングがしづらくなります。すると、歯垢が溜まりやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。特に、前歯の歯並びが悪くなると、見た目にも影響を及ぼすため、注意が必要 です。
3-3 歯並びの悪化を防ぐための対策
親知らずが歯並びに悪影響を与えないようにするためには、定期的な歯科検診と適切な対策が重要 です。
定期的な歯科検診を受ける
親知らずの生え方を把握し、歯並びに悪影響を与える可能性がある場合は、早めに対策を講じることが大切 です。特に、レントゲン検査を受けることで、親知らずの状態を正確に判断できます。
親知らずの抜歯を検討する
親知らずが歯並びを押してしまっている場合や、今後悪化するリスクがある場合は、抜歯を検討することも選択肢の一つ です。
特に、以下のケースでは、抜歯が推奨されます。
- 親知らずが横向きに生えている場合
- 歯並びがすでに乱れ始めている場合
- 痛みや違和感が続く場合
3-4 矯正治療と親知らずの関係
歯列矯正を考えている場合、親知らずの影響を事前に確認することが重要 です。
矯正治療前に抜歯が必要な場合がある
歯列矯正を行う際に、親知らずが邪魔になっていると、抜歯が必要になることがあります。特に、親知らずが歯列の後ろから圧力をかけることで、矯正後の歯並びが乱れる可能性があるため、事前に対策をとることが重要 です。
矯正後の歯並び維持のためのケア
矯正後に親知らずが生えてくると、せっかく整えた歯並びが再び乱れてしまうことがあります。矯正治療後の歯並びを維持するためにも、親知らずの管理は重要なポイント です。
4. 炎症が広がると起こるリスクとは
親知らずの周囲で発生した炎症は、適切な処置を行わないと周囲の組織に広がり、深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。炎症が拡大すると、歯茎だけでなく、顎や全身にも影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。
この記事では、親知らずの炎症がどのように進行し、どのようなリスクをもたらすのかについて詳しく解説します。
4-1 炎症が広がる主な原因
親知らずの炎症が進行してしまうのは、適切なケアが行われていなかったり、細菌の感染が悪化してしまうためです。
親知らず周辺の清掃不足
親知らずは奥に位置するため、ブラッシングが不十分になりやすいです。その結果、食べかすやプラーク(歯垢)が溜まり、細菌が繁殖しやすくなります。
細菌感染の悪化
炎症を引き起こす細菌が、歯茎や顎の骨に入り込むことで、より深刻な炎症へと発展 することがあります。特に、免疫力が低下していると、感染が急速に広がるリスクが高まるため注意が必要です。
4-2 炎症が広がると起こる口腔内のトラブル
炎症が広がると、口腔内でさまざまな症状が現れます。早期に適切な対応をしないと、さらに悪化する可能性があるため、注意が必要です。
歯茎の腫れと痛みの悪化
初期の炎症では軽い腫れや違和感にとどまりますが、炎症が拡大すると歯茎が大きく腫れ、激しい痛みが生じることがあります。食事や会話が困難になる場合もあります。
膿の発生(膿瘍)
炎症が進行すると、細菌が膿を作り、膿瘍(のうよう)が発生することがあります。膿瘍ができると、歯茎が腫れ、強い痛みや口臭を引き起こすため、早急な治療が必要です。
4-3 顎や顔面への影響
炎症が広がると、顎の骨や顔全体に影響を及ぼす可能性があります。
顎の骨への感染(骨髄炎)
細菌が顎の骨にまで感染すると、「骨髄炎(こつずいえん)」という状態を引き起こします。骨髄炎は強い痛みを伴い、治療が遅れると手術が必要になることもあるため、早期対応が重要 です。
顔の腫れや変形
炎症が拡大すると、頬や顎が腫れ、顔の形が変わってしまうことがあります。特に、化膿した炎症が広がると、皮膚の表面にも影響を及ぼし、顔の一部が赤く腫れ上がることもあるため、注意が必要です。
4-4 炎症が全身に及ぼすリスク
口腔内の炎症は、局所的な問題にとどまらず、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
細菌感染による発熱や倦怠感
炎症が悪化すると、細菌が血流に乗って全身へ広がり、発熱や倦怠感などの症状が現れることがあります。この状態は、「敗血症(はいけつしょう)」と呼ばれ、放置すると命に関わることもあるため、速やかな治療が必要です。
免疫力の低下による感染症のリスク
炎症が慢性化すると、体の免疫機能が低下し、ほかの感染症にもかかりやすくなる可能性があります。特に、高齢者や持病のある人は、体調不良の原因にもなり得るため、早めの対応が求められます。
5. 親知らずが引き起こす顎の痛み
親知らずは、顎の痛みを引き起こす要因の一つです。親知らずが正常に生えていない場合や、炎症を伴うと、顎関節や筋肉に負担をかけ、痛みが発生することがあります。さらに、放置すると噛み合わせの問題や顎関節症のリスクが高まるため、適切な対処が必要です。
この記事では、親知らずが原因で起こる顎の痛みのメカニズムと、それに伴うリスク、適切な対処法について詳しく解説します。
5-1 親知らずによる顎の痛みの原因
親知らずが生えることで顎に痛みが生じる原因はいくつか考えられます。特に、親知らずが正しく生えていない場合や、周囲に炎症が発生している場合は注意が必要です。
親知らずの圧迫による痛み
親知らずが横向きや斜めに生えると、隣の歯や顎の骨を圧迫し、痛みが発生することがあります。特に、埋伏(まいふく)した状態の親知らずは、周囲の歯や組織を押し続けるため、慢性的な痛みを引き起こす可能性があります。
炎症による痛み
親知らずの周囲は清掃が難しく、細菌が繁殖しやすい環境です。その結果、炎症が発生し、歯茎が腫れたり、顎全体に痛みが広がることがあります。この状態を智歯周囲炎(ちししゅういえん)といい、悪化すると強い痛みや発熱を伴うこともあります。
5-2 顎関節に及ぼす影響
親知らずの問題が悪化すると、顎関節(がくかんせつ)に影響を与え、さらに深刻な症状を引き起こすことがあります。
噛み合わせの乱れ
親知らずが正しく生えていないと、歯並びが乱れ、噛み合わせに影響を与えることがあります。噛み合わせが悪くなると、片側の顎ばかりに負担がかかり、顎の痛みが慢性化する可能性があります。
顎関節症のリスク
親知らずが原因で噛み合わせが変化すると、顎の関節に過度な負担がかかり、顎関節症(がくかんせつしょう)を引き起こす可能性があります。顎関節症になると、口を開け閉めする際に痛みを感じたり、関節がカクカクと音を立てることがあります。
5-3 親知らずの痛みを和らげる対処法
顎の痛みが親知らずによるものである場合、早めに対策を行うことで症状の悪化を防ぐことができます。
痛みを和らげる応急処置
顎の痛みが強い場合は、以下の方法で一時的に症状を和らげることができます。
- 冷やす:炎症がある場合、氷や冷たいタオルを顎に当てると、腫れや痛みが軽減します。
- 市販の鎮痛薬を服用する:ロキソプロフェンやイブプロフェンなどの鎮痛剤を服用すると、痛みを和らげることができます。
- 刺激物を避ける:辛い食べ物や硬い食事は顎に負担をかけるため、できるだけ避けるようにしましょう。
歯科医院での診察を受ける
顎の痛みが続く場合は、歯科医院を受診し、適切な処置を受けることが重要です。歯科医院では、レントゲン検査を行い、親知らずの状態を確認します。以下のような治療方法が検討されることがあります。
- 親知らずの抜歯:痛みや炎症が繰り返される場合、親知らずを抜くことで根本的な解決につながることがあります。
- 抗生物質の処方:炎症が強い場合、抗生物質を服用して細菌の増殖を抑える治療が行われることがあります。
5-4 親知らずによる顎の痛みを予防する方法
親知らずが原因の顎の痛みを予防するには、日頃のケアと定期的な検診が大切です。
親知らずの状態を定期的にチェックする
親知らずが生えている場合、定期的に歯科医院でチェックを受けることが重要です。親知らずの向きや位置を確認し、必要に応じて抜歯の判断を早めに行うことができます。
口腔ケアを徹底する
親知らず周辺は磨き残しが多くなりやすいため、歯磨きやフロスを丁寧に行うことが大切です。特に、歯間ブラシや洗口液を活用すると、細菌の増殖を抑える効果があります。
6. 口臭と親知らずの意外な関係
口臭の原因にはさまざまな要因がありますが、親知らずもその一因となることがあります。特に、親知らずが正常に生えていなかったり、炎症を起こしていたりすると、口臭が悪化する可能性が高くなるのです。
この記事では、親知らずと口臭の関係、口臭のメカニズム、対策方法について詳しく解説します。
6-1 親知らずが口臭を引き起こす原因
親知らずが口臭の原因となるのには、いくつかの要因があります。親知らずの位置や状態によって、細菌が繁殖しやすくなり、口臭が発生しやすくなります。
親知らず周辺の汚れの蓄積
親知らずは、口の一番奥に生えてくるため、歯磨きがしにくい部位です。そのため、食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすくなり、細菌が増殖しやすくなります。細菌が増えると、揮発性硫黄化合物(VSC)という悪臭の元となるガスが発生し、口臭が強くなるのです。
親知らずの炎症による悪臭
親知らずが半分埋まった状態や、斜めに生えている場合、歯茎との間に隙間ができ、そこに細菌が繁殖します。この状態が続くと、炎症が発生し、「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼ばれる状態になることがあります。炎症が起こると、膿(うみ)や出血が生じ、それが口臭の原因となるのです。
6-2 口臭の原因となる親知らずのトラブル
親知らずが口臭の原因になる具体的なトラブルとして、次のようなケースが考えられます。
埋伏(まいふく)親知らずと口臭
埋伏親知らずとは、歯茎の中に完全に埋まっている親知らずのことです。一見、問題がなさそうに見えますが、歯茎の下で炎症を起こしている可能性があります。炎症が慢性化すると、歯茎の腫れや膿が発生し、悪臭を伴うことがあるのです。
生えかけの親知らずによる口臭
親知らずが一部だけ生えている場合、歯茎との間に隙間ができ、食べかすや細菌が溜まりやすい状態になります。これが続くと、歯周病のような症状が進行し、口臭が発生しやすくなります。
親知らずの虫歯による口臭
親知らずは、奥にあるため虫歯になりやすく、治療が難しい歯です。虫歯が進行すると、歯の内部で細菌が繁殖し、腐敗臭のような口臭が発生することがあります。
6-3 親知らずによる口臭を防ぐ方法
親知らずが原因の口臭を防ぐには、日頃のケアと適切な治療が重要です。
正しい歯磨きとケア
親知らず周辺を清潔に保つためには、通常の歯磨きだけでなく、特別なケアが必要です。
- 歯間ブラシやフロスを使用する
親知らず周辺に溜まった汚れを取り除くために、歯間ブラシやフロスを活用しましょう。通常の歯ブラシでは届きにくい部分の汚れを取り除くことができます。
- 殺菌作用のあるデンタルリンスを使う
口内の細菌の繁殖を防ぐために、殺菌作用のあるデンタルリンスを活用すると効果的です。特に、クロルヘキシジンやセチルピリジニウム塩化物(CPC)を含む洗口液が推奨されます。
親知らずの炎症を防ぐための対策
親知らずが原因で炎症が起きている場合、早めに対策を行うことが大切です。
- 口腔内を清潔に保つ
炎症を悪化させないために、食後はしっかりと歯磨きをし、口腔内を清潔に保つことが重要です。
- 腫れがある場合は冷やす
歯茎が腫れている場合は、冷たいタオルや氷を使って患部を冷やすと、炎症を抑えるのに効果的です。
6-4 親知らずによる口臭が続く場合の対応
親知らずが原因で口臭が続く場合は、早めに歯科医院を受診することが大切です。
歯科医院での診察と治療
歯科医院では、親知らずの状態を確認し、必要に応じて治療を行います。
- 親知らずの抜歯
炎症が繰り返し発生する場合、抜歯が最善の解決策となることが多いです。抜歯をすることで、口臭の原因を根本から取り除くことができます。
- 抗生物質の処方
親知らず周辺で細菌感染が起きている場合、抗生物質を服用して炎症を抑えることがあります。
7. 親知らず周辺の歯周病リスク
親知らずは、口の中の奥に位置するため汚れが溜まりやすく、歯周病のリスクが高い歯です。特に、親知らずが正常に生えていない場合や、埋まっている状態では、歯周病を引き起こす要因となることが多くあります。
この記事では、親知らず周辺の歯周病リスクと、それを防ぐための対策について詳しく解説します。
7-1 親知らずが歯周病を引き起こす原因
親知らずが歯周病の原因になる理由はいくつかあります。
磨き残しが発生しやすい
親知らずは奥歯のさらに奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが発生しやすい場所です。特に、斜めに生えている親知らずや、半分埋まっている状態の親知らずは、歯茎との間に食べかすが詰まりやすく、細菌が繁殖しやすい環境になります。
歯茎の炎症が進行しやすい
親知らずが不完全に生えている場合、歯茎が部分的に覆いかぶさることがあります。この部分は、細菌が繁殖しやすく、歯周病の初期段階である歯肉炎を引き起こす可能性が高くなります。さらに、炎症が進行すると、歯周ポケットが深くなり、歯周病へと発展してしまうのです。
7-2 親知らずが原因で起こる歯周病の症状
親知らず周辺の歯周病は、一般的な歯周病と同じような症状を引き起こしますが、より痛みや腫れを伴うことが多いのが特徴です。
歯茎の腫れと出血
親知らずが原因で歯周病が進行すると、歯茎が赤く腫れ、歯磨きの際に出血することがあります。これは、細菌が繁殖し、歯茎に炎症を起こしているサインです。
口臭の悪化
親知らず周辺で細菌が増殖すると、口臭がひどくなることがあります。これは、歯周病菌が発生させる揮発性硫黄化合物(VSC)が原因で、腐敗したような悪臭を放つことがあります。
顎の違和感や痛み
歯周病が進行すると、炎症が顎の骨にまで及ぶことがあり、痛みを伴うことが多いです。特に、親知らず周辺で歯周病が悪化すると、顎が腫れたり、口が開きにくくなることもあるため、注意が必要です。
7-3 親知らずが原因の歯周病を防ぐ方法
親知らず周辺の歯周病を予防するためには、日頃のケアと適切な対処が重要です。
正しい歯磨きとデンタルケア
- 歯ブラシの選び方
親知らず周辺は磨きにくいため、ヘッドが小さく奥まで届きやすい歯ブラシを選ぶことが大切です。
- 歯間ブラシやフロスの活用
歯と歯の間の汚れをしっかり落とすために、歯間ブラシやフロスを使用すると効果的です。
- 殺菌作用のあるデンタルリンスの使用
細菌の増殖を防ぐために、クロルヘキシジンやCPCを含むデンタルリンスを活用すると、歯周病のリスクを抑えることができます。
歯科医院での定期検診とクリーニング
- 親知らずの状態をチェックする
親知らずが歯周病を引き起こしている場合、定期的に歯科医院でチェックを受けることが重要です。
- 歯石除去(スケーリング)を受ける
親知らず周辺に歯石が溜まると、歯周病が悪化しやすくなるため、歯科医院で歯石除去(スケーリング)を受けるのが有効です。
- 抜歯の検討
親知らずが歯周病の原因となっている場合は、抜歯が最適な治療法となることもあります。特に、炎症が繰り返し起こる場合や、他の歯に悪影響を及ぼしている場合は、早めに抜歯を検討することが推奨されます。
8. 親知らずが原因で発生する嚥下障害
親知らずは、奥歯の奥に位置するため、歯並びや噛み合わせに影響を与えることがあります。その結果、口の機能が低下し、**食べ物をうまく飲み込めない「嚥下障害」**を引き起こすことがあります。
この記事では、親知らずと嚥下障害の関係、起こりうるリスク、そして予防策について詳しく解説します。
8-1 親知らずが嚥下障害を引き起こす原因
噛み合わせの乱れによる影響
親知らずが正しく生えていない場合や、斜めに生えている場合、噛み合わせに悪影響を及ぼします。噛み合わせが乱れると、食べ物を適切に咀嚼できず、飲み込みにくさを感じることがあります。
また、片側だけで噛む癖がつくと、顎に負担がかかり、嚥下機能のバランスが崩れる可能性があります。
炎症による喉の違和感
親知らずが腫れている場合、口の奥が狭くなり、食べ物をうまく飲み込めなくなることがあります。特に、親知らず周辺の炎症(智歯周囲炎)が悪化すると、喉の違和感や飲み込む際の痛みが発生しやすくなります。
炎症が広がると、扁桃腺や舌の動きにも影響を与え、より嚥下が困難になることもあります。
8-2 親知らずが原因で起こる嚥下障害の症状
食べ物を飲み込む際の違和感
親知らずによる炎症があると、食べ物を飲み込むときに引っかかるような違和感を感じることがあります。特に、硬いものや大きな食べ物を飲み込むのが難しくなり、食事がしづらくなることがあります。
喉の痛みや腫れ
炎症が進行すると、喉の奥に痛みを感じることがあります。これは、親知らずの周囲の細菌が広がり、喉の粘膜に影響を与えるためです。
食事中のむせやすさ
噛み合わせが悪くなることで、食べ物が適切に咀嚼されず、大きな塊のまま喉へ流れやすくなります。この結果、むせやすくなり、誤嚥(食べ物が気道に入る)を引き起こすリスクも高まることがあります。
8-3 親知らずが原因の嚥下障害を防ぐ方法
正しい噛み合わせを維持する
- 片側だけで噛まないように意識する
- 親知らずの影響で片側噛みが癖にならないよう、両側の奥歯を均等に使うことを意識しましょう。
- 歯科医で噛み合わせの調整を行う
- 噛み合わせが悪化している場合、歯科医院で適切な調整を受けることが大切です。
親知らず周辺の炎症を防ぐ
- 正しい歯磨きと口腔ケアを徹底する
- 親知らず周辺の汚れをしっかり除去するために、歯間ブラシやデンタルフロスを活用しましょう。
- デンタルリンスを使用する
- 抗菌作用のあるデンタルリンスを使い、細菌の繁殖を防ぐことが重要です。
- 痛みや腫れを感じたら早めに歯科受診
- 親知らずが原因で痛みや違和感がある場合、早めに歯科医院で診察を受けることが嚥下障害の予防につながります。
9. 未処置の親知らずが全身に与える影響
親知らずは、必ずしも抜歯が必要なわけではありません。しかし、適切な処置を受けずに放置すると、口腔内だけでなく、全身に悪影響を及ぼすことがあります。特に、炎症や細菌感染が進行すると、思わぬ健康トラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、未処置の親知らずが引き起こす全身への影響と、それを防ぐための対策について詳しく解説します。
9-1 未処置の親知らずが引き起こす全身トラブル
細菌感染による全身の炎症反応
親知らずが適切に生えておらず、炎症を繰り返すと、歯茎の細菌が血流を通じて全身に広がることがあります。これにより、以下の健康リスクが高まります。
- 心臓病(細菌性心内膜炎)
口内の細菌が血管を通じて心臓に達し、心内膜炎を引き起こす可能性があります。特に、心臓に持病がある人は注意が必要です。 - 関節炎やリウマチの悪化
口腔内の細菌が関節に影響を与え、関節炎を悪化させる可能性が指摘されています。 - 免疫力の低下
持続的な炎症が続くと、免疫システムに負担をかけ、風邪や感染症にかかりやすくなることもあります。
顎関節症のリスク
親知らずが歯並びに影響を与え、噛み合わせが乱れると、顎関節に負担がかかり、顎関節症の原因となることがあります。
- 顎の痛みや違和感
親知らずによる圧迫で顎関節に歪みが生じ、口の開閉がスムーズにできなくなることがあります。 - 頭痛や肩こりの原因に
顎のズレが首や肩の筋肉に負担をかけ、慢性的な肩こりや頭痛を引き起こすこともあります。
9-2 未処置の親知らずが引き起こす生活への影響
睡眠障害のリスク
親知らずの炎症や痛みが慢性化すると、就寝中に痛みを感じることがあり、熟睡できなくなる場合があります。
- 歯ぎしりや食いしばりの原因に
親知らずの違和感がストレスとなり、無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしてしまうこともあります。
食事や発音への影響
親知らずの痛みが続くと、食事中に噛む力が低下し、栄養摂取が不十分になることがあります。
- しっかり噛めないことで消化不良に
咀嚼回数が減ると、胃腸への負担が増え、消化不良を起こしやすくなります。 - 発音のしづらさ
親知らずの痛みや腫れが原因で、口の開閉がスムーズにできず、発音に影響を与えることもあります。
9-3 未処置の親知らずによる全身への影響を防ぐ方法
定期的な歯科検診を受ける
- 親知らずの位置や生え方をチェック
レントゲン検査を受け、将来的に問題が生じるリスクがないか確認しておくことが重要です。
親知らず周辺のケアを徹底する
- 歯間ブラシやデンタルフロスを活用
親知らずの周囲は歯ブラシが届きにくいため、補助的なケアが必須です。 - 抗菌作用のあるデンタルリンスを使用
細菌の繁殖を防ぐことで、炎症のリスクを低減できます。
10. トラブルを防ぐためにできること
親知らずは、放置すると炎症や痛み、歯並びの乱れなどさまざまなトラブルを引き起こす原因になります。適切なケアを行い、定期的に歯科検診を受けることで、親知らずに関連する問題を未然に防ぐことができます。
この記事では、親知らずのトラブルを防ぐためにできる具体的な対策について詳しく解説します。
10-1 親知らずを健康に保つためのセルフケア
正しい歯磨きを徹底する
親知らずは奥歯の奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすい部分です。適切なケアを行うことで、炎症や虫歯のリスクを軽減できます。
- 歯ブラシの角度を工夫する
親知らずの周囲をしっかり磨くためには、歯ブラシの毛先を斜めに当てて細かく動かすことが重要です。 - 歯間ブラシやデンタルフロスを活用
親知らずの周りには歯垢が溜まりやすいため、フロスや歯間ブラシを使って清潔に保ちましょう。 - デンタルリンスで口内の殺菌を行う
抗菌作用のあるマウスウォッシュを使用すると、親知らず周辺の細菌繁殖を抑えることができます。
10-2 定期的な歯科検診を受ける
親知らずの状態をチェック
親知らずの生え方には個人差があり、横向きに埋まっていたり、半分だけ生えていたりするケースもあります。定期的に歯科医院でレントゲン撮影を行い、親知らずが問題を引き起こしていないか確認することが重要です。
- 定期的な検診を受ける頻度
親知らずに問題がない場合でも、年に1〜2回は歯科検診を受けることをおすすめします。 - 炎症や痛みがある場合は早めに相談
違和感を感じたら、放置せずに歯科医院で相談しましょう。
必要に応じて抜歯を検討
すでに親知らずが炎症を起こしている場合や、将来的に問題を引き起こす可能性が高い場合は、抜歯が推奨されることがあります。
- 抜歯のタイミングを見極める
痛みや腫れが出る前に計画的に抜歯することで、リスクを最小限に抑えることができます。 - 抜歯後のケアも大切
抜歯後は、適切なケアを行い、感染やドライソケット(血餅が取れることで起こる強い痛み)を防ぐことが大切です。

親知らずの管理で健康な口腔環境を維持しよう
親知らずは、生え方や位置によっては特に問題なく過ごせる場合もあります。しかし、親知らずが原因で虫歯や炎症が起こると、放置することでさらに深刻なトラブルへと発展する可能性があります。定期的に歯科検診を受け、自分の親知らずの状態を正しく把握することが大切です。
この記事で紹介したように、親知らずが引き起こすリスクを理解し、適切なケアや処置を行うことで、健康な口腔環境を維持できます。違和感や痛みを感じた場合は、早めに歯科医に相談しましょう。親知らずとうまく付き合いながら、将来の歯の健康を守りましょう!

執筆者
内藤洋平
丘の上歯科醫院 院長
平成16年:愛知学院大学(歯)卒業
IDA(国際デンタルアカデミー)インプラントコース会員
OSG(大山矯正歯科)矯正コース会員
YAGレーザー研究会会員